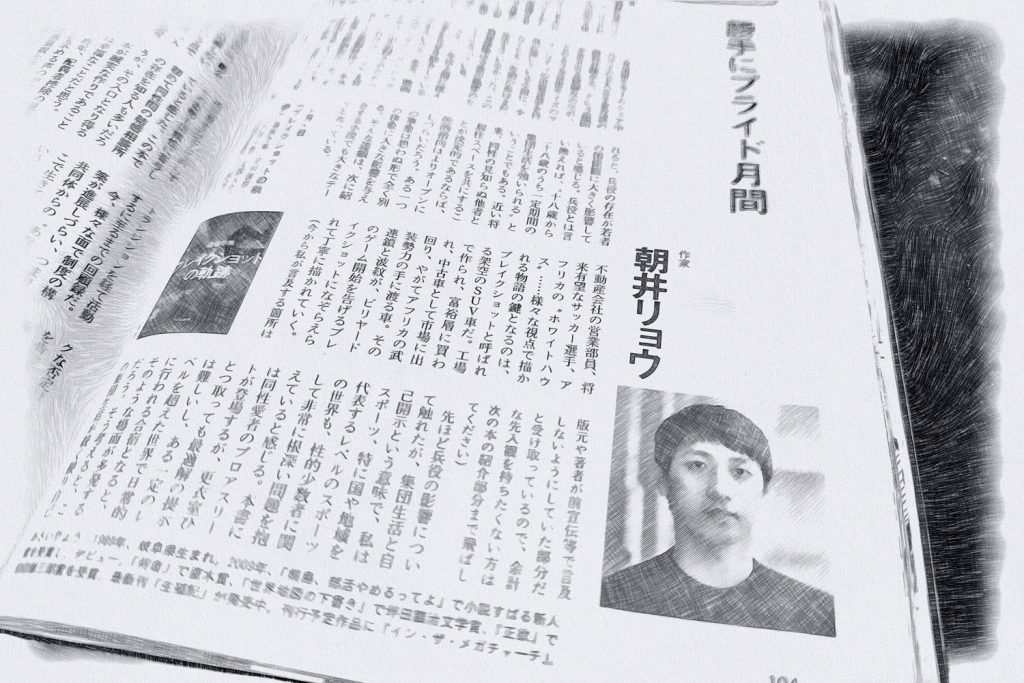
作文でいちばん難しいのは、書評だと思う。とくに長い小説の書評なんて、その作品の特性や面白さを、言葉で伝えるのは骨が折れるし、書き手はどこかで頓挫しがちである。常に原作者の意図に対する無謀なる挑戦という踏み絵がちらつく。尤も、小説というのは、構造主義的な理屈を絡めていうと、“原作者への理解”など実にナンセンスなものなのだというくらいに作為的であり、その何かを知ることは不可能――ということは百も承知のうえである。
朝井リョウさんのプライド書評
敬愛する作家の朝井リョウさんはそのエッセイにおいて「勝手」に、「プライド月間」を開催した。毎度おなじみ『週刊文春』の「私の読書日記」(2025年7月17日号)である。ああ…といって、ここで本を閉じてしまう人と、どれどれ? と思って、最後まで読み通す読者に二分されるかもしれない。「プライド月間」と聞いて、読むのをためらってしまう人、あるいはやめてしまう人は、一定数いると思う。そういうことも想像しながら、私はこれを読んだ。
「私の読書日記」の朝井リョウさん執筆の番で、「勝手にプライド月間」というタイトルであった。LGBTQ+のセクシュアリティに関連した大変興味深い本を、朝井さんは今回5作品紹介している。つまり5冊の本である。まずはタイトルを列挙しておこう。
- パク・サンヨン著『大都会の愛し方』(亜紀書房)
- 逢坂冬馬著『ブレイクショットの軌跡』(早川書房)
- 田岡智美著『素敵なご縁に恵まれて結婚やめました』(KADOKAWA)
- 長尾莉紗著『PAGEBOY エリオット・ペイジ自伝』(DUBOOKS)
- 太田尚樹著『グレーとライフ』(イースト・プレス)
で、今回私が述べたいのは、「書評を書くこと自体難しい」ので、朝井さんがそれらの本の読後に感じたことやいいたいことが、なんとなくどれも中途半端で締められてしまっているな、という点だ。尚、これは反面悪い意味ではない。朝井さんはことばを選んでいる。書評自体がそもそも難しい。どうしても遠慮気味に“ことば足らず”になってしまったりもする。結果、彼のことばのいい回しが、なんとなく淀んで、難しくなってしまっているのではないかと思ったのだ。
そこで、ちょっと馬鹿げた試みかもしれないが、朝井さんのそれぞれの本の感想の、“最後の段落”だけ抽出してみることにする。
パク・サンヨンの大都会の愛し方
韓国のフィクションに触れると、兵役の存在が若者の価値観に大きく影響していると感じる。兵役とは言い換えれば、“十八歳から二十八歳のうち一定期間の集団生活を強いられる”ということでもある。近い将来、同性の見知らぬ他者と居住スペースを共にすることが決定的であるならば、性的指向はよりオープンにしづらいだろう。ある一つの事象は思わぬ形で全く別の事象に大きな影響を与える。そんな連鎖は、次に紹介する小説でも大きなテーマとなっている。
朝井リョウ「勝手にプライド月間」より引用
小説家らしい視点だ。
小説家らしく、物事の「価値観」と「事象」と「影響」の変化が気になってしまうのだろう。マイノリティでなくても、同性・異性を問わず他者との共同生活においては、性的指向はオープンにしづらいものではないだろうか。昔と比べて今の若者たちは、「性的な」ものへの関心を建前上薄っぺらくし、それをほとんど語りたがらないのは、世の中の「多様性」らしさと自己との因果関係を直接結びつけることは、かなりリスクを伴うから――と判断しがちなのだ。
逢坂冬馬のブレイクショットの軌跡
LGBTQ+の話となると「愛することは自由だ」みたいな帰結が用意されることもままあるが、そんなことは当然で、そのうえで解像度を上げて丁寧に考えなければならないことが山のようにあると感じる。
朝井リョウ「勝手にプライド月間」より引用
この段落の文章が示していることの、文脈としてはこういうこと――。
朝井さんはこの本『ブレイクショットの軌跡』で同性愛者のプロアスリートが登場する旨を述べ、マイノリティ特有の自己開示の《根深い問題》があって、更衣室のやり取りを想像すれば、《最適解の提示は難しいし、ある一定のレベルを超えた世界で日常的に行われる合宿となると、そのような場面が多発するのだろう》とも述べる。すなわち、異性愛者が多い居住スペースの中に、同性愛者が放り込まれることの《根深い問題》という観点である。
その観点は、単眼的な見方ではないのか。
居住スペースの中にいる同性の見知らぬ他者が、どの人も異性愛者かどうか、実際わからないはずだ。先述したように、性的指向は同性・異性を問わず、そもそも他者に開示しづらいものなのである。他者は皆、自己開示済みだが、マイノリティの自分はなかなか開示しづらいよね、という見方は、単眼的としかいいようがない。実際のところ、ほとんど皆、開示できていないではないか――と考えるべきである。
「解像度」というワードが最近よく世間で飛び交うが、思想や思考の「解像度」を「上げる」とは、いったいどういう意なのか。私にはよくわからない。
思うに、その「解像度」を上げたところで、見えているもの自体は全く同じものであり、単に物事の精細度の緻密さがはっきりしてくるだけの話ではないか。ぼんやりと見えているもの(あくまで開示されているもの)に関しては、よく近づいてじっくりと観察すれば、それがはっきり見えてくることもあるだろう。しかし、そもそも見えていないもの(はじめから開示されていないもの)に関しては、いくら「解像度」を上げても、見えるはずがないのである。
そういう意味合いで、私は、本来的な「掘り下げる」ということばと、流行りことばとしての「解像度」がどの点でどう違うのか、よくわかっていない。自分でよくわからないから、こうした流行りことばをうっかり使ったりすることはできないのだ。
それともう一つ、「愛することは自由だ」という帰結に関しても、都合のいい話の代表格である。
むろん朝井さんはそれを半分貶して、もっと物事をよく見て明らかにしていこうという主旨であるかと思われる。
ただ、このことで付け加えておきたいのは、先の「解像度」ということばと同様、なんとなくごまかされてしまいそうなのだが、マイノリティに限らず、世の中すべからく愛することは自由――と思い込みすぎないほうがいいということだ。
それをいうなら、「愛することを考えるのは自由」である。
考えるだけなら自由だ。愛とは、親しい者どうしだけが共有しうるもの。それ以外の他者に接する時には、お互いの同意と懇意と熱意とが必要であり、愛は決してそこらじゅうに自由にあるべきものではなく、相手構わず無法地帯の無礼講サービスでもない。
恋愛に関していうと、実にそれは不思議かつ複雑怪奇なものであって、自由ではないからこそ、そうなのである。例えば既婚者の不倫を、誰しもが認めないのは、その証左である。法律の規定があるからのみではない。心情的に揺さぶられ、乱され、結論としてそれは罪深く、許されるものではない、と考えるからだ。とはいえ、もっと別個の心情にも気づくはずだ。たしかに罪深いけれど、自分のあの時の感情は不倫への兆しではなかったかと――。あるいは罪深いパートナーであるがゆえに、より愛情を掻き立てられ、真の愛に目覚めたり、逆に一切合切目が覚めて、愛情など最初から無かったのに、なぜ私は貴方を恨むのか――などと気づいたりもして、要するに恋愛はそうそう単純なものではないのである。
ともかく、「愛することは自由」と、LGBTQ+の恋愛観をごちゃ混ぜにしていくのは、物事の見方が表面的で短絡で、乱暴な論理ではないかと思う。はき違えないように注意が必要である。
田岡智美の素敵なご縁に恵まれて…
昨年、配偶者控除の見直しを求める声の中に「制度が価値観を作る」という主旨のものがあった。私自身、人間の価値観は「世の中にそういう制度があるから」というところから形成される部分も大きいと感じている。制度の存在というのは、共同体からの“あなたはここで生きていけますよ”というメッセージでもある。現状、同性婚の実現がいつになるかわからないが、このようなサービスが存在することから形成される価値観は必ずあると思う。
朝井リョウ「勝手にプライド月間」より引用
最後の文章が奇妙ないい回しになっていて、おや? と思った。同性婚の制度(の実現)で形成される「価値観」は、必ず「ある」と思う――??
その制度が実現しても、人々が活用しなければ意義はないと思われるが、同性婚の需要は「ある」という意味なのか、単に思想的な「価値観」だけのことなのか。
例えば、同性の、性的指向が異性愛者の二人――女好きの男Aと女好きの男Bの二人、又は、男好きの女Cと男好きの女Dの二人――が、なんらかの機会に意気投合し、ちょっと同姓婚してみようかと思いつく。そういう新しい「価値観」のことか。
結婚の選択肢がひろがり、異性愛あるいは同性愛にかかわりなく、同性結婚するカップル――という新種のライフスタイルが持ち込まれた時、家族や家庭はどのように形成されるのか、ということを、朝井さんはいいたかったのか。
そうなると、いわずもがな、結婚と恋愛感情とは直接結びつけない、ライフスタイルの選択肢を拡張しただけのこととなるだろうが、そういう意味での選択肢が増えるのも、やぶさかではないと私は思う。むしろ画期的なことだ。
とはいいつつ、あえて述べる。
すでに半分実現してしまっているのだ。ライフスタイルにおいて、つまり、法的に認められた「異性どうしの結婚」において、そこに恋愛感情がいっさい絡まないカップルのこと。カップルというより、同じ家に住む「同伴者的関係」の契約。大半の家庭がそうであるとは、口が滑っても申し上げない。が――。
だから原則論として、〈愛情問題と婚姻とは別物である〉と、子どもの頃に教育していたほうが、世の中の事情――これを大人の事情ともいう――がわかりやすくなって、もっと話が早かったはずである。ならば、同性どうしだって、かまわないじゃないかと。愛情は別個の問題で、関係ないのであれば。
長尾莉紗のPAGEBOY…
最近米国ではLGBTQの青少年や若年成人向けの自殺防止相談サービスの予算廃止が決まった。あなたはここで生きていけますよ、の一つの喪失である。このようにハッキリ明言されなくても、貴方をあなたとして生かすための制度はありません、というメッセージは絶え間なく性的少数者の足元に絡み付く。先述した兵役やスポーツの世界の強制的集団生活もその一つだろう。この、ドラマチックな否定はなくとも、存在を肯定するような制度そのものもないために、他者には見えない疲弊が積み重なっていく状態のことをどう表現すればいいのか。読みながら考えていた。
朝井リョウ「勝手にプライド月間」より引用
私という個人は、団塊ジュニア世代に挙げられる一人である。
なので、かつて学生時代に、
「はい皆さん、ここにいる10名のうち1名だけ採用しますから、いいですか、そうですね、あなたとあなたとあなたたち9名は、不採用ですので帰ってよろしいです。お疲れ様でした」
といったようなことを、あっちこっちでいわれ続けてトラウマにもならなくなった経験が、ゴロンゴロンと山のように積まれた、そういうごっつい人生を歩んできている――からして、つまり、LGBTQ+の排外的な差別問題を横目に、それと全く同様、自己の意志とは無関係なところで排斥されてしまう困難さについては、心情的によく理解しているつもりである。
数打ちゃ当たるの希望的観測もなく、百発百中、該当せず。不採用。不合格。不適格。一人ひとり個別の理由があっての「不」なのではなく、はなから決められていた「不」。ヒトの数が多すぎるから、あなたたちは最初から「不」なのよ、という理不尽極まりない「不」。つまり、敗者復活の余地もない頑なな絶対的拒否。ふるい落とされた私たちは、塵と同然なのだった。
存在すなわち生存そのものが認められていないのではないかという恐怖が常にある。疲弊は当然あるが、トラウマにもならない。むしろ、強くなる。「自律的に知恵を絞らなければ生きていけない」という野性的な本能が覚醒したりもするのだ。そういうタフな面が培養されてきた世代が、団塊ジュニアの隠れた記号なのではないだろうか。むろん、塵となって風と共に消えた脱落者も多い。
だから、排外主義は絶対にノーなのだ。
太田尚樹のグレーとライフ
今度生まれるかもしれない傾斜を理由に制度に反対するより、今そこにある傾斜を緩めるための議論をしたい。その議論自体がきっと、誰かのメンタルヘルスに手を差し伸べている。
朝井リョウ「勝手にプライド月間」より引用
なんだかもう、力尽きてしまいそうな話になってきている。わかりづらい。『グレーとライフ』の本自体を読み込まなければ何のことだか、よくわからない。
「傾斜を緩める」議論をすること自体が、きっと誰かの「メンタルヘルス」に「手を差し伸べている」――のかも?
ちょっと本の存在が、勿体ない気がしてきた。性的少数者は、常にメンヘラと対峙して――と思い込み過ぎることは、あまりいいことではないのではないかと思えてくる。
多かれ少なかれ、人類とはかわいそうな生きものの集団であることは、地球誕生以来間違いない事実だが、LGBTQ+がとくに“かわいそうな人たち”の象徴として、記号化されて扱われるのは筋が違うのではないか。そういう一元的な「価値観」こそ、捨て去るべきではないのか。
そもそも、LGBTQ+の人々が、恋愛感情だけで生きているわけではないことを、私たちは理解しておく必要がある。ひょっとすると当事者も、ただそれのみの感情に突き動かされて、メンヘラと対峙してしまう人は少なくないかもしれない。
作家は売れる本を書くために、あらゆるものに対してメンヘラ対峙のストレス社会像を作り上げていく。小説が真実を暴き立てるツールであるとは、古今東西、誰もいっていないはずだが、昨今の世界的潮流では、そういう装置としての小説が、たいへん流行っているように私は感じる。そもそも地球も人類も、メンヘラ対峙を観念化する以前に、絶望的なストレス症候群の存在であることを忘れてはならない。
ともかく昨今の潮流に対して、単に売れる本を書いているだけの、一カテゴリーだとしか私は思わないようにしている。
§
朝井さんの作家的な熱情のこもった文脈には、それなりの人工的な調味料や合成甘味料が多分に含まれていることを、私は一ファンとして経験的によく知っている。朝井さんにかかわらず、ベストセラー作家はそのような特性が鍛錬されているからこそプロなのである。そのこともよくわかっている。
だとすれば、そのプロのまな板に、何かしらのマイノリティの話が乗っかった場合、読み手はきわめて用心すべきだ。何がスパイスとして振りかけられたかを――。
例として、「愛は自由なもの」と誤謬の沙汰を伏線的にばらまいておき、それはそうではないとお盆をひっくり返す。小説の大技小技とは、そういうものであり、その術の面白さこそがエンタメであり、ベストセラーとなりうる手練手管である。しかし、だ――。
その材料として、LGBTQ+がいつも担がれる理由はない。
「プライド月間」であればこそ、用意されたカテゴリーを取っ払った、小説ジャンルとしてではない「価値観」が必要なのではないだろうか。彼ら少数者は、まだ社会に打ち解け合っている状態とはいえない困難さがあるにせよ、彼らのほうもまた、多数派のへんてこな性的指向を面白おかしく語りたがっているのだから。
関連記事
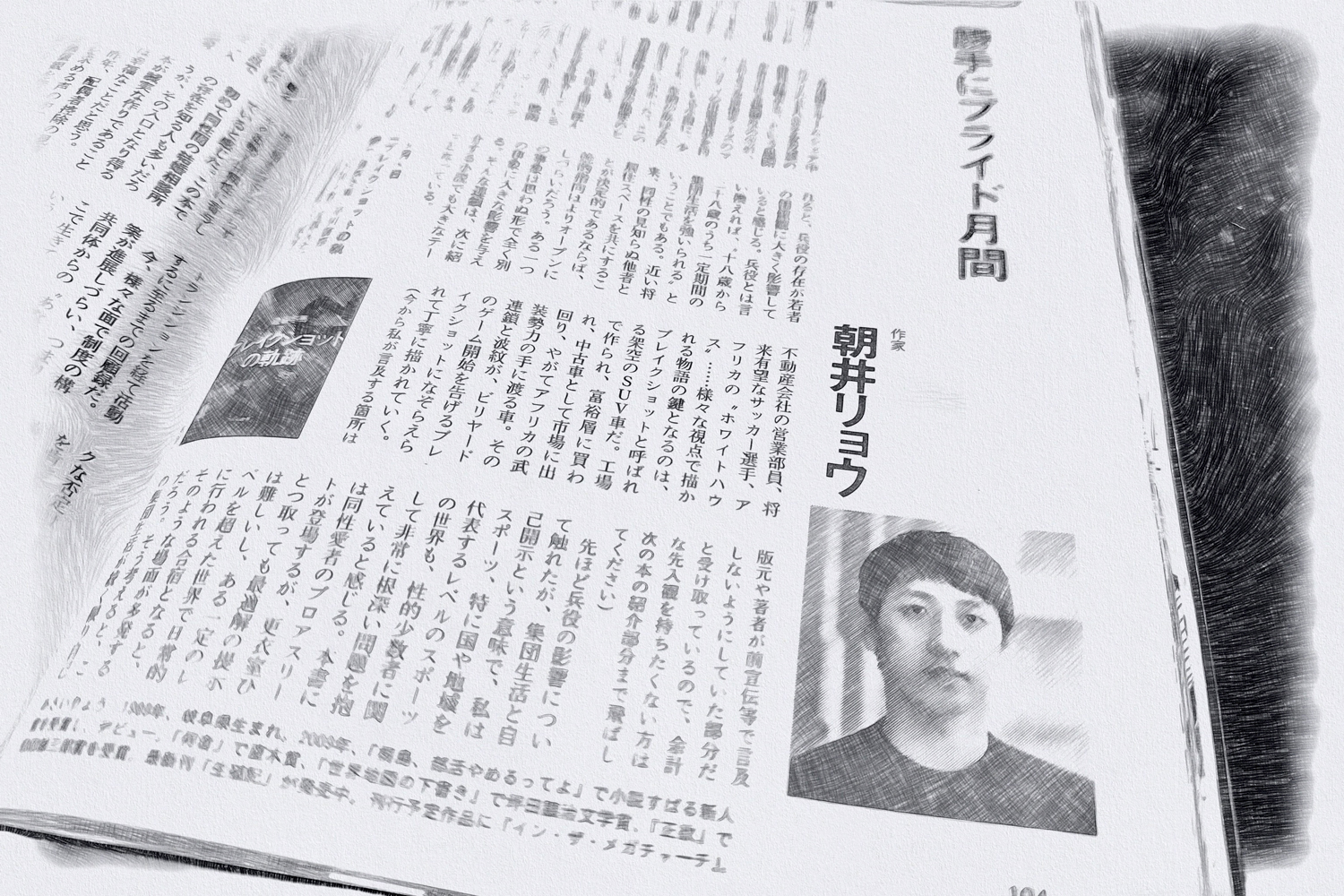


コメント