
もはや、精緻な器官による皮膚感覚というべきものに、身悶えしてしまう――。
食べるもの、すなわち口に入れていただくものへの感謝の念がこもっていて、その食材の細部にこだわり、鋭い感性を発揮してしまう岸本さんは、日本人的な、万物に至らしめる霊性とやらの存在に、その世界を明け渡してしまうのだった。
もうおなじみ、翻訳家でエッセイストの岸本佐知子さん。
筑摩書房のPR誌『ちくま』2025年9月号(No.654)のコラム「ネにもつタイプ」のタイトルは、「慈悲心」。
あらかじめ、「慈悲」(じひ)とは何かを記しておく。三省堂の『新明解国語辞典』(第八版)にはこう出ている。
《「慈」は衆生に楽を与える意、「悲」はその苦を取り除く意》で、《仏・菩薩が衆生をいつくしみ、あわれみをかける心。「慈悲心」》
捨ててはいけないネギのアソコ
テレビである料理番組を観た岸本さん。
「茄子の炒め物」で、それに飾る「白髪ネギ」を作る途上――。
長ネギの白い部分を5センチほどに切って、切れ目を入れ皮を開いた時、その料理人はなんと、芯の部分は使わないからと、ネギの真ん中の部分を「ぽい」と捨てたそうだ。
岸本さんは、それを見て立ち上がった――。
あのネギの真ん中の筒状の部分は「きびがら」に似ていて、小学校のずこうの時間がよみがえる、らしい。
はて――。
すきやきを食べる時に、ネギを噛みしめると、あれがつるっと皮の中から飛び出て、口に甘みが広がるそうな。
《長ネギの中でも一番素敵と言っていいあの部分を、捨てるというのか》
それを読んだ私などは、長ネギをそんなふうに見つめて考えたこともないので――焼鳥のネギマは別――岸本さんの《捨てるというのか》の気持ちがわかりかねる不届き者なのだけれど、それが「きびがら」に似て、何故ずこうの時間を思い出すのかわからなかった。私はこれを読んだ時点で、一種の敗北感を味わったというか、白旗を上げたのだった。
岸本さんにいわせれば、「捨ててはいけない」食べ物の部分は他にもあって、たぶんその食べ物の部分が「捨てないで」と叫んでしまっているのだろう。
読んでいくとそれは、《空豆の莢の中のふわふわクッション》だったり、メロンの中心部にある《モール状のもしゃもしゃ》だったり、《トウモロコシのあの髪の毛》だったり、マンゴスチンという果物の果肉を入れた殻だったりする。
その殻など、《職人が丹念に磨き上げたオーク材。あの白くてデリケートな果肉を入れるために、こんな立派な家をこしらえるとは》と、驚嘆するのであった。
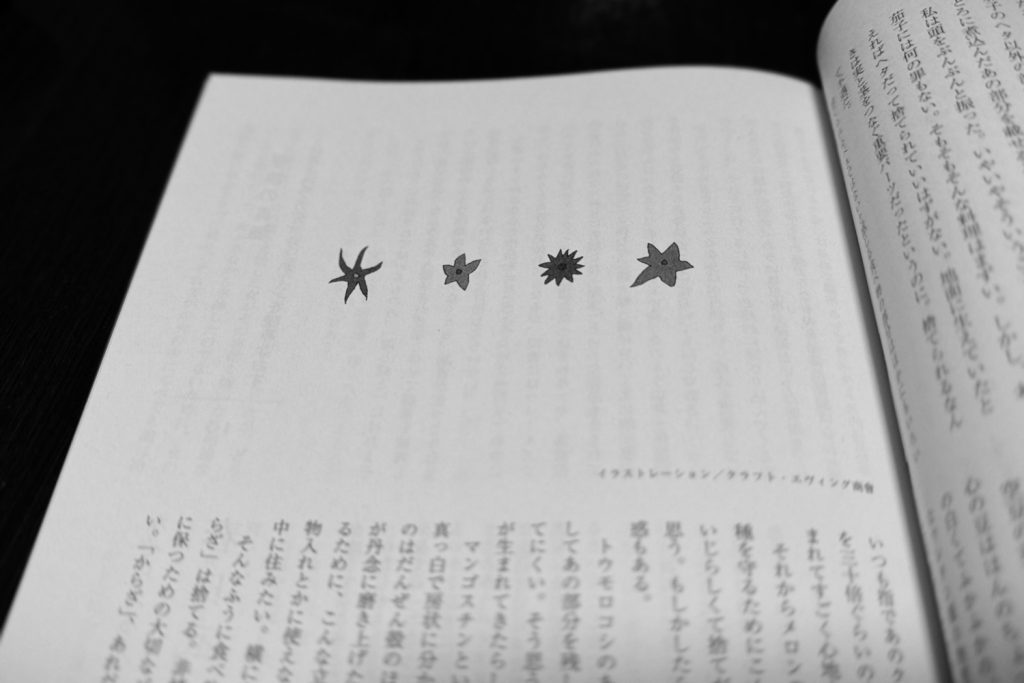
信楽焼のたぬき
食べるのに、そういう固くて消化の悪そうなものは、捨てるしかないと思うが、ヘチマ(糸瓜)などは、乾燥させた線維性の果実の部分を台所などで使う洗浄用のたわし(束子)にしたりするし、ひょうたん(瓢箪)は酒の入れ物にしたりするのは知っている。
ほら、信楽焼のたぬきの置物。
笠を被ったたぬきが片手に通い帳、もう片方に徳利を持っているでしょう。あれです。あの徳利は、ひょうたんで出来ているでしょう。あの中にお酒が入っているのです。
信楽焼のたぬきの置物は、「八相縁起」といって、福を呼び込む招き猫と同じで――まあだいたい、商売繁盛を願う商いをする店に置かれていたりするね。ほら、ちゃんと金袋持ってるね。
え? どこにあるかって?
それはまあじっくり、たぬきの置物を眺めてみてくださいな。私だってじっくり眺めたことなんかなかったが、ぶらぶらとしているはずだから。
§
考えてみると、ひょうたんの徳利などは少し意味が違う気もするが、口に入れるものに限らず、昔の人はモノを捨てるより、なにかそれを再利用する観念に向けられていたのではないか。
モノには全て魂(精霊?)があると――。
それが、「環境に優しい」という観念と結びついていたかどうかは別である。が、リサイクル・スピリッツは大切かもしれない。
とはいえ、慈悲深い岸本さんでも、鶏の卵の「からざ」は、容赦なく捨てるという。《非情に捨てる。即座に捨てる》。
「からざ」は本当は、食べてよろしいもので、むしろ栄養素が豊富だそうな。でも岸本さんは違う。理屈抜きで、あれは捨てるらしい。
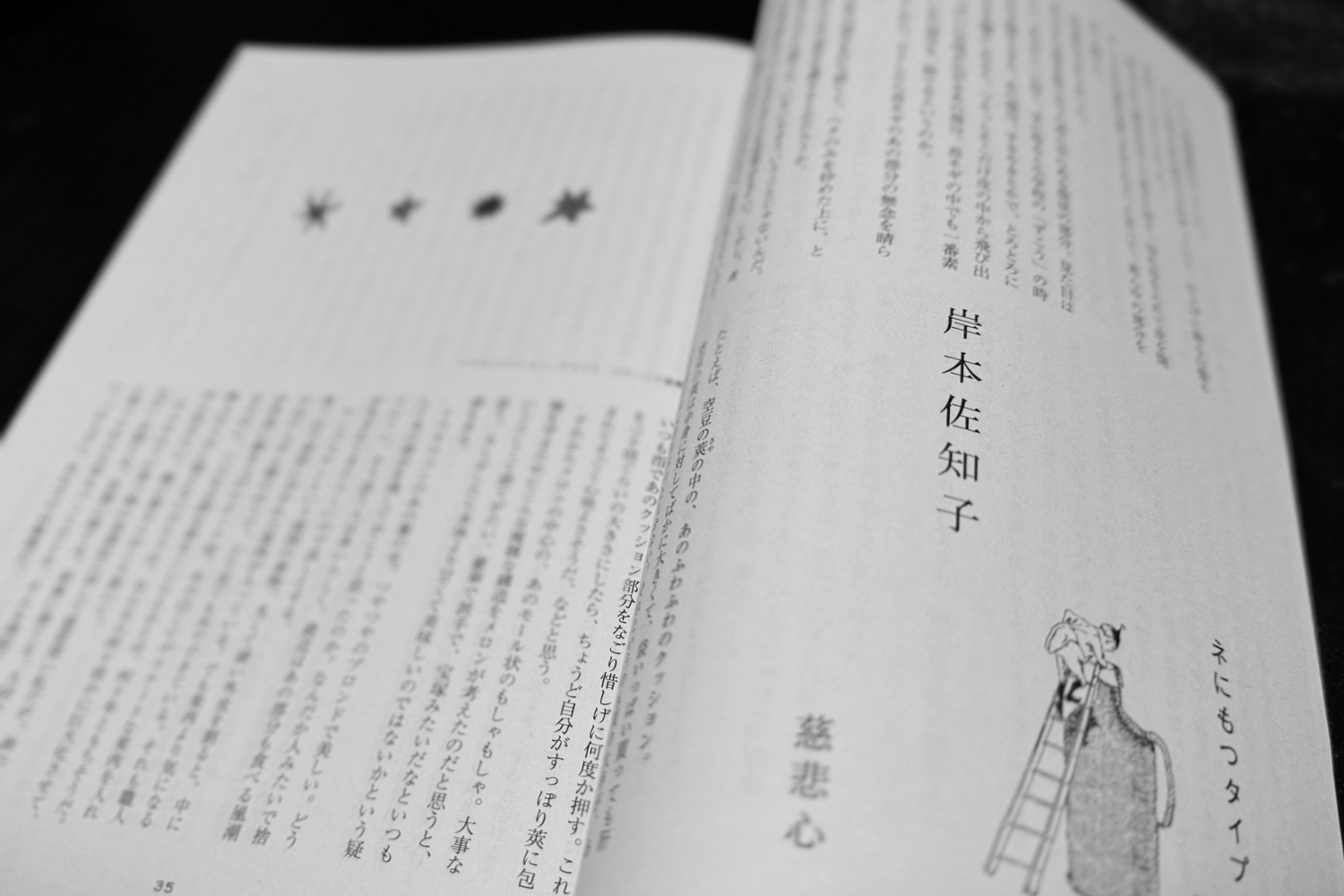


コメント