ごく最近、ジョン・アーヴィング(John Irving)の『ホテル・ニューハンプシャー』(“The Hotel New Hampshire”)と『サーカスの息子』(“A Son of the Circus”)の文庫本を買った。『サーカスの息子』の文庫本(新潮文庫)は上下巻となっており、訳者は岸本佐知子さんである。
それは奇想天外なストーリーらしく、日本語訳としてはアーヴィングと岸本さんの運命共同体のような文学世界が醸し出されているのではないかと、自ら読む日を楽しみにして、期待しているところだ。
さて、筑摩書房のPR誌『ちくま』2025年10月号(No.655)のコラム「ネにもつタイプ」。タイトルは「工作員」。いうまでもなく、このコラムの筆者は、翻訳家でエッセイストの岸本さん。
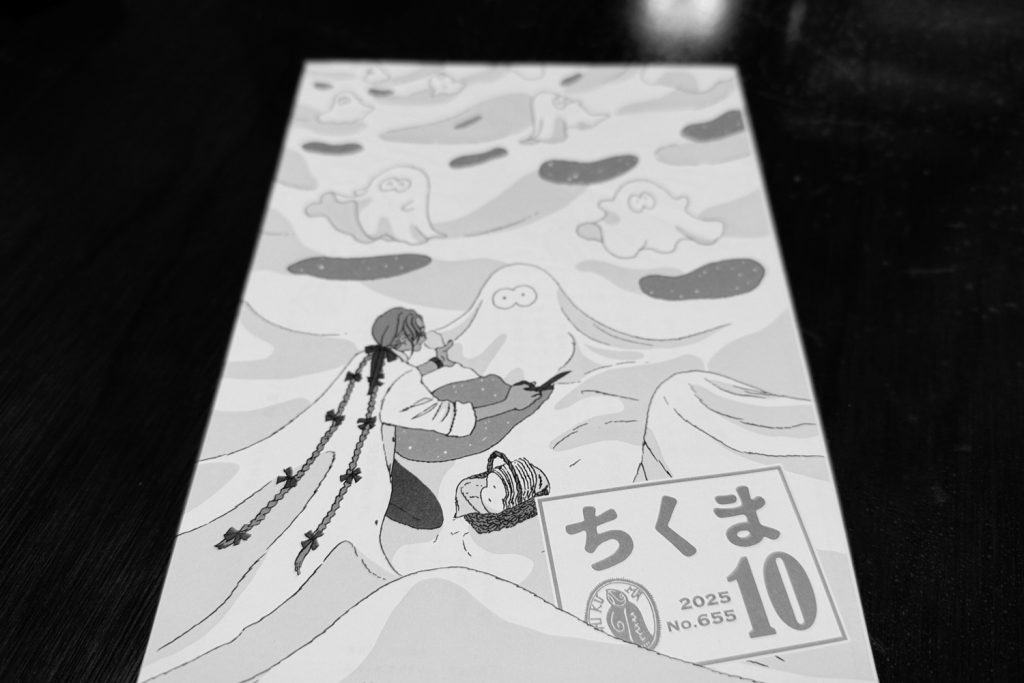
対人恐怖症
こんな話。
岸本さんが近所の行きつけのクリーニング店に行くと、見慣れていた年配の女性の店員さんがいなくなっていたという。体型はふくよかで、よく喋って話しかける店員さんだったらしい。服を持っていくと、必ず服の感想を述べ、そのセンスを褒めてくれた。
面白いことに、普段岸本さんは、あまり人から話しかけられるのが苦手なのだという。それをこんなふうに述べる。
《社交に使うエネルギーを惜しんで、店などでもなるべく仏頂面で、「話しかけるな」オーラを全身から出している》
でも岸本さんは、その女性の店員さんに関しては、ちっとも嫌ではなかったらしい。クリーニング店に行くのが楽しみだったくらいに…。それなのに、なぜその人はいなくなっていて、違う人に変わっていたのか。
私もアガり症でした
話の腰を折る。
もし人に話しかけられるのが苦手、アガってしまう、喋れない、億劫といったような意味での対人恐怖症の度合いの数値が、バババッと出る装置なり便利なアプリがあるならば、私などはほとんど「0%」に近い数値がはじき出されて、なんにも面白いことはないだろう。
私の場合、相手が初対面だろうと女性だろうと、外国人だろうと、日本で憲政史上初めての女性総理大臣だろうと、たぶんアガらないと思う。ここでアガってほしい! と思うくらいに、アガらない。
つまり、対人には、動揺しなくなってしまったのである。大抵、〈この人とは昔から知り合いだったのではないか〉と相手から思われるくらいに、普通にけっこうな時間の会話が、平気で続けられてしまうのである。語弊を恐れずにいうと、“初対面”に関しては不干渉なのである。
ただし――若い頃は全然真逆だった。
小学校の4年生の時に、学級委員をやらされ、緑色のバッチを胸元に付けられ、ホームルームの司会なり、“はなしあい”の議事進行なりをやらされたのだけれど、それらをどう務めてよいかわからず、しどろもどろになって赤面し、とにかく人見知りが激しかった。
そういうアガリ症みたいなのは高校生くらいまで続いて、書店に行っても恥ずかしくて「エロ本が買えない」とか、ドラッグストアで「コンドームが買えない」とか、対人恐怖症の度数は95%くらいあったのではないかと思われる。
そんなかわいらしい面影は、いったいどこへいってしまったというのか――。
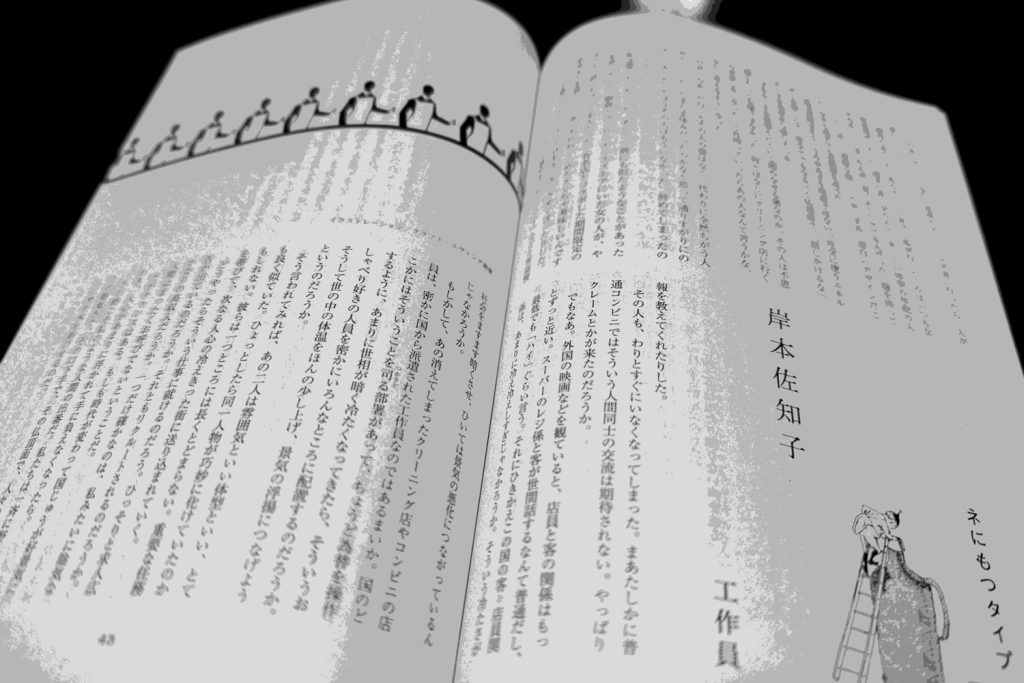
消えた店員さん
以前岸本さんは、駅前のコンビニでも同じようなことがあったという。
やはりその店員さんも女性で、よく話しかけてくる人で、まるで店内インフルエンサーかのように、期間限定の商品をおすすめしてくれたり、あれやこれやと商品の有益情報を教えてくれたりしたらしいのだが、すぐにその人もいなくなってしまったのだという。
岸本さんが“社交エネルギー0%キャンペーン中”にもかかわらず、意外と好感が持てた店員さんほど、いなくなってしまうという怪現象。これらについて、さぞショックかと思いきや、案外そうでもない。岸本さん曰く、《薄くがっかりした》。薄く――。
しかしながら岸本さんは、こんなことを思うのである。
外国の映画を観れば、スーパーのレジ係と客が、ふつうに話したりしている。それに比べて日本では、客と店員の関係が冷え冷えしすぎていないか?
そうはいったって、さっきまで岸本さんは、店では「話しかけるな」オーラを全身から出しているとか、いっていたじゃないか――。ねえ、どっちがいいのさ、岸本さん。
ともかく、冷え冷えの社交の日本。
《そういう冷たさが社会をますます暗くさせ、ひいては景気の悪化につながっているんじゃなかろうか》
ふーん。
ここで岸本さんは、とんでもない妄想を抱くのだった。
行きつけのクリーニング店やコンビニで消えてしまった女性店員さんたち。実は彼ら、国から派遣された工作員(こうさくいん)なのではないか、と。
工作員…。
国のどこかにそういう部署があって、世相が暗くなってきたら、おしゃべりな人を隠密にあっちこっち全国に配置する活動。そうして世の中の体温を上げ、景気浮揚につなげる――。
ふーん。
岸本さんは、こんなこともいっている。あの二人、雰囲気も体型もよく似ていたな、と。もしかして、同一人物が化けていたのかも。まさに工作員。
工作員…。
それは誰がそうさせているのか
私もあまり乗り気ではなかったが、一応調べてみた。工作員。辞書をひくと、こう出ていた。
情報の収集、敵側のスパイ活動の防止その他秘密の活動をする人。
三省堂『新明解国語辞典』第八版より引用
国からとか、特別な組織で雇われて工作員になった人(?)以外に、普段どこにでもいるような温和な人の中にも、まるで工作員みたいに心中鋭く、物事に目論見を持っていたり企図したり、策士だったりする人――私はいるなあと思っている。
とどのつまり、そういう人というのは、スパイ映画の観過ぎで、自分をエージェントか何かになぞらえて、ただの仕事をコソコソと労働してみたり、意味もなくエレベーターで地下に行ったり屋上に上がったり、駐車場の車の陰に隠れてみたり、黒っぽい服を着てみたり、街なかで他人の視線を〈自分は監視されている〉と思い込んでみたり、昼食中に隣の人の他愛ない話をありもしない妄想に膨らませてみたり、とにかくそうやって自分で自分を楽しんでいるだけなのであった。まさか自宅に、縄梯子なんてないよね? でもいいじゃない、それで。
そのことはともかくとして、岸本さん。こんなことを書いている。
もし、逆に世の中の景気がよくなり、人々が浮かれてきたら――。
その時は、私の出番です――。
この文章を書いている岸本さんが、机の前でひょいと手を挙げた姿が、容易に想像できた。こんなこともいっている。
《私たちは一斉に野に放たれ、その陰気さで、その口下手で、その仏頂面で、人々の浮かれた気持ちに冷水を浴びせるのだ》
これを俗にいう陰キャ、というやつかもしれないが、“私たち”なんていわないで、どうか独りでやってほしい。
まあ、でも、頼もしい。
そうなったら岸本さん、この仕事、どうするのでしょう。「ネにもつタイプ」の執筆とか。
§
真面目な話、私は思う。
こんなこといったら誰かに叱られるかもしれないが、女性で、パートタイマーで、突然急に仕事辞めちゃったりする人って、大概、その人のせいじゃない。おそらく、ダンナか、子どものせいです。
女性はあまり文句をいわず、そういう時は、スッと華麗に、辞めていくものなのである。そして大概、男性の上司だったら、文句をたれるね。なんで急に辞めるの、こっちの仕事、回んないだろって。
あんたたちオトコ連中が、ちゃんと家事をこなし、子どもの面倒を逐一見てくれていたら、女性はそんなつまらぬことで、会社を辞めたりなんかしないのだよ。
そんな時、家庭に帰れば、「話しかけるな」オーラを夫が発していて、陰気で、口下手で、仏頂面。子どもたちもなんとなくイライラしていたりして、そういう気不味い家庭内の空気を良くするために、誰かが工作員みたいに思われるのって、日本ではよくあるのだ。あるある――な図式。
といったところで、なるべく早く岸本さん訳の、アーヴィングの小説読みたいなあと、ふわふわ思っている今日このごろなのでございます。はい、おわります。
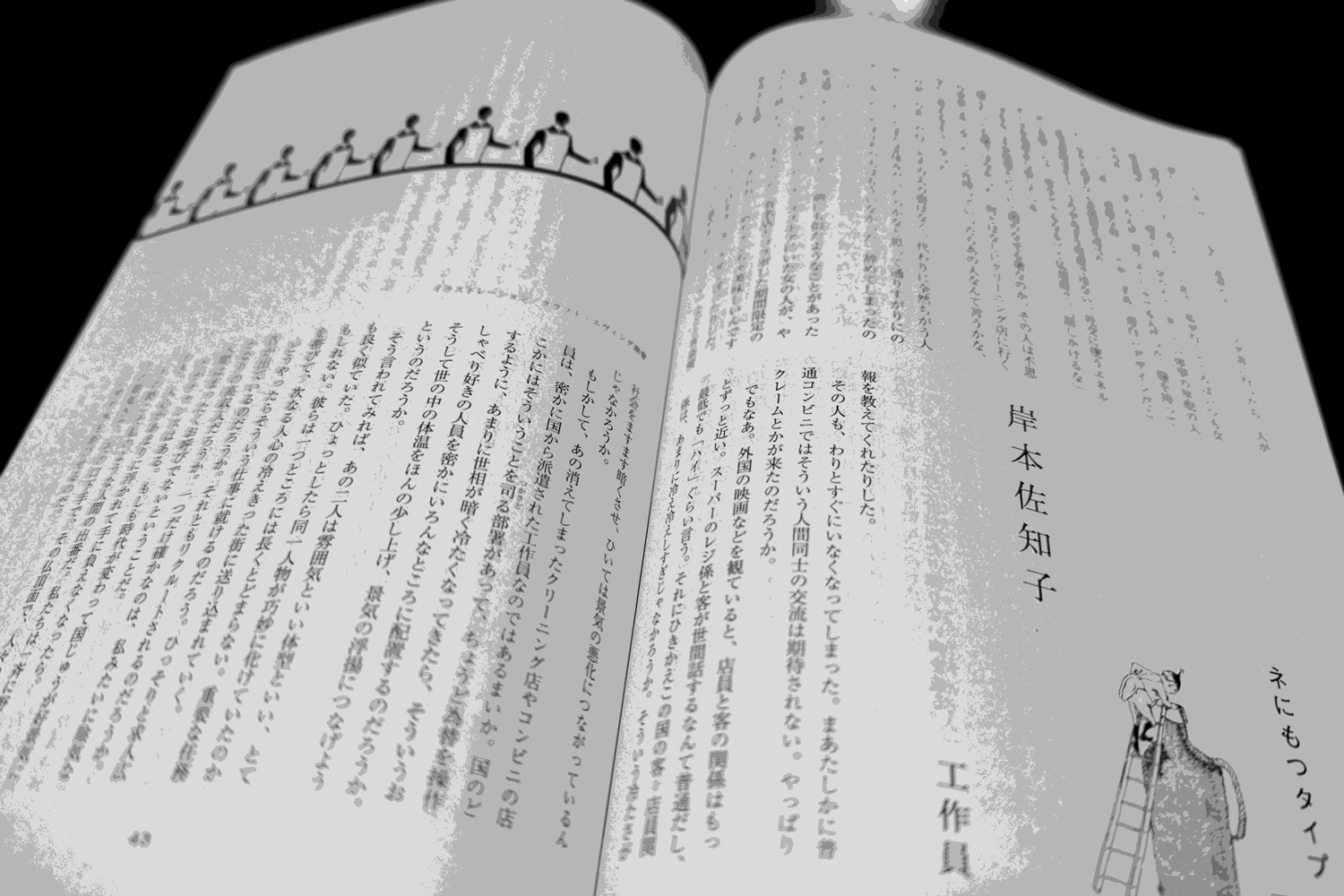

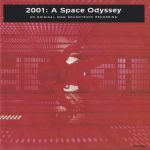
コメント