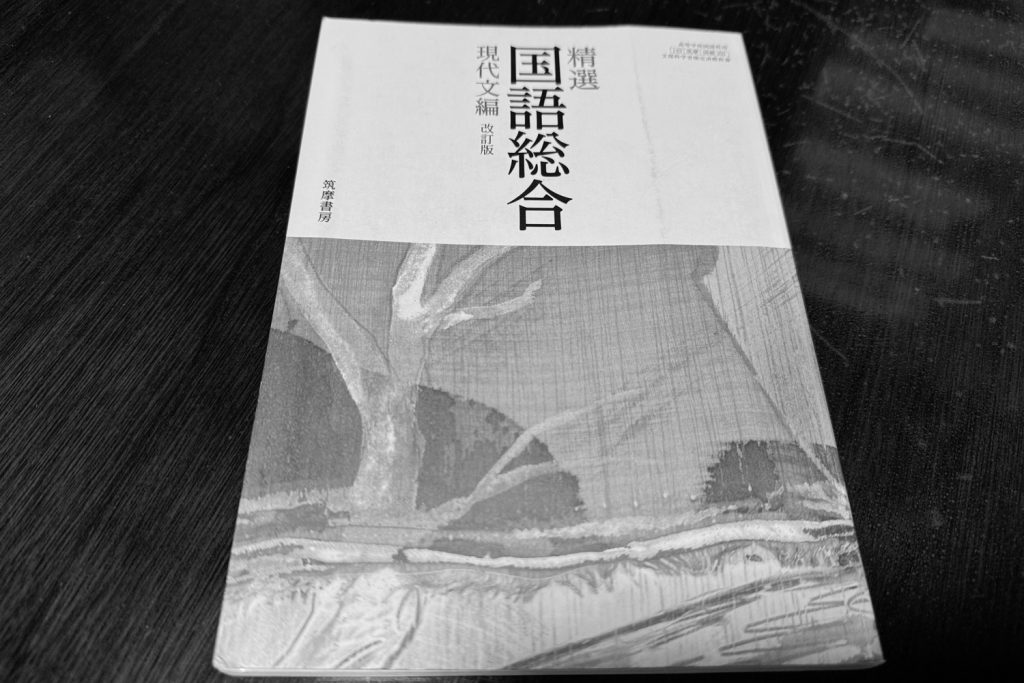
日増しに、先々の長編小説など書けないと思ってしまう。いや、一週間ごとにそう思うのだ。名の通った文人方々の作品なり評論なりに目を通していると、自分のちっぽけな存在が木っ端微塵に吹っ飛ぶのである。
書けないが――書きたい。
そんな時、私が逃げ込むのは、国語の教科書だ。あわよくば、気を紛らわすため、何か一つ技術でも方策でも、盗みたい心境なのである。手に取ったのは、高校の国語教科書『精選 国語総合 現代文編 改訂版』(筑摩書房/2020年発行)であったり…。
名前を付けてカタログ化するということ
内田樹氏の評論「ことばとは何か」は、手堅い――というか、日本語文体の安息すら感じるのだった。ことばに関して、たいへん重要なことが示されている評論文である。
彼はまず聖書を引用し、ヒト以外の生き物に名前が付けられていく、そういうことばの原理主義的な働き、そして言語学者で哲学者であるフェルディナン・ド・ソシュール(Ferdinand de Saussure)の「名称目録的言語観」の話を持ち出す。
要するに、ヒトが勝手気ままに、ものに名前を付けていき、カタログ化していったこと。それはヒトの生活の便宜上、そういうものだ、そうするべきものだ――ということについて述べられている。
マトンがあるからシープ肉とはいわない
ただし、日本語では「犬」(イヌ)と呼ぶ生き物を、英語圏ではdogといい、フランス語圏ではchienと呼んでいて、そこにことばの正当性はなく、それぞれの言語圏で呼び方は千差万別である、ということでもある。
名前を持たないものは、実在しない(もの)とソシュールは考えたという。日本語で「羊」(ヒツジ)なるものは、フランス語で「ムートン」といい、英語では興味深いことに「シープ」と「マトン」があり、「マトン」は食用羊肉を指す。
名前になっていなければ、それを(その生き物を)思考したりできない。概念化もできない。
語義というのは同義語という意味で相関関係にありつつ、《含まれている意味の厚みや奥行が違う》ことがある。
先の「羊」の場合、食用は「羊肉」といい、“ヒツジ”の“肉”それ以上でもそれ以下の意味も示唆もないが、英語圏でそれを「シープ肉」とは呼ばずに「マトン」といいかえるのには、それなりの文化的感覚的蓄積において、《含まれている意味の厚みや奥行が違う》のだ。ただし、日本でも「羊肉」を「マトン」と称するようになり、文化的おこぼれをいただいている。とはいえ、本質的にはやはり、そのことばを使うかぎりにおいての、語義の含みに相違ない。
こうした背景から、ソシュールは、ことばの「価値」(Valeur)と呼び、signification=「語義」とは少し異なることを示唆している。
ゆえに、あることばが付けられた時に初めて、そのものは「生まれた」のであり、思考され、概念化される。驚くべき帰着として、ものは、「ことばから生まれる」のだった。
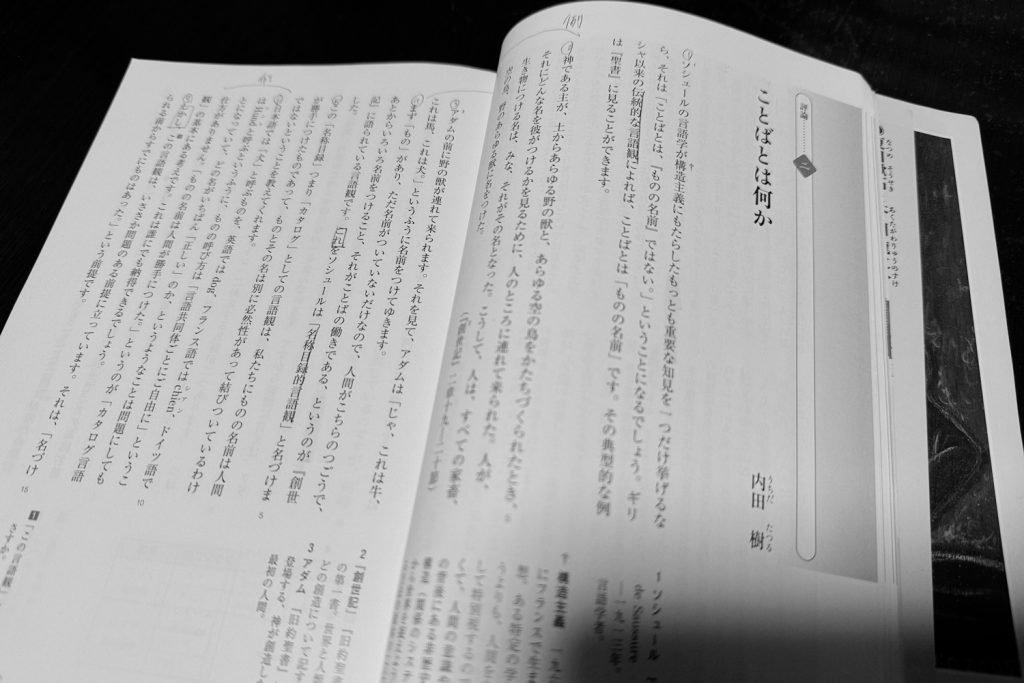
話さないということは生きていないということ
ことばは、そのもののかたちを見いだすと同時に、切れ目を入れる。ソシュールは述べる。
それだけを取ってみると、思考内容というのは、星雲のようなものだ。そこには何一つ輪郭のたしかなものはない。あらかじめ定立された観念はない。言語の出現以前には、判然としたものは何一つないのだ。
ソシュール『一般言語学講義』より
言語表現(主体は歌や話しことば)を発展させたものとして、手話(sign language)がある。両手や指、あるいは上半身を使って視覚的に表現する言語である。日本ではごくごく近年、法的にも言語(視覚言語)として規定されたばかりだ。
いずれにしても、歌や話しことばの音声言語以外に、手話という視覚言語による伝達手段があり、これによって対話の可能性は大いに拡充されたことになっている。
しかしながら実際、仕事や生活の中で、ほとんど何も話さない人たちがいる。
ものは「ことばから生まれる」というソシュールの言説を借りれば、言語表現を敢えて放棄し、自分という存在を消してしまっている人たちは、いわば「透明な存在の市民」といえないか。ヒトは本来、何らかの不自由さや不遇の境地から、言語表現の可能性を発明していき、近代以降発展を遂げた――と考えるべきだろうが、現代人には時折既に、「話す」ことも、また「書く」ことも放棄しつつある「透明な存在の市民」がいるのだ。私はまだ、彼らの生存の領域を、どのように考えたらいいか、よくわからない。
伝達手段はかろうじて備わっているはずである。しかし、「対話」を好まない(=否定している)人たちがいる。それは非対話の日常化だ。
インターネットは国境や人種を問わず情報交換を著しく波及させる効果があるが、「対話」を好まない彼らは、そこからも逸脱し、オフラインの生活を営んでいたりする。こうなると、言語としてのモチベーションは、オフラインかつ非対話主義で最小限に抑えられ、その縮んだ理性の中で生活を送ることになる。彼らにとって、幸福はどこから生み出されるのだろうか。いや、私はあえていうが、不幸であるといわざるを得ないのだ。
言語表現に対して消極的な態度を取るということは、何ら共同体に与しないということになる。実存を否定した「価値」に、ことばが留められてしまっているのだ。このような逆説的な実体験からも、ことばがいかに大事か、そしてものは「ことばから生まれる」ことを感覚的に理解できるのである。
関連記事
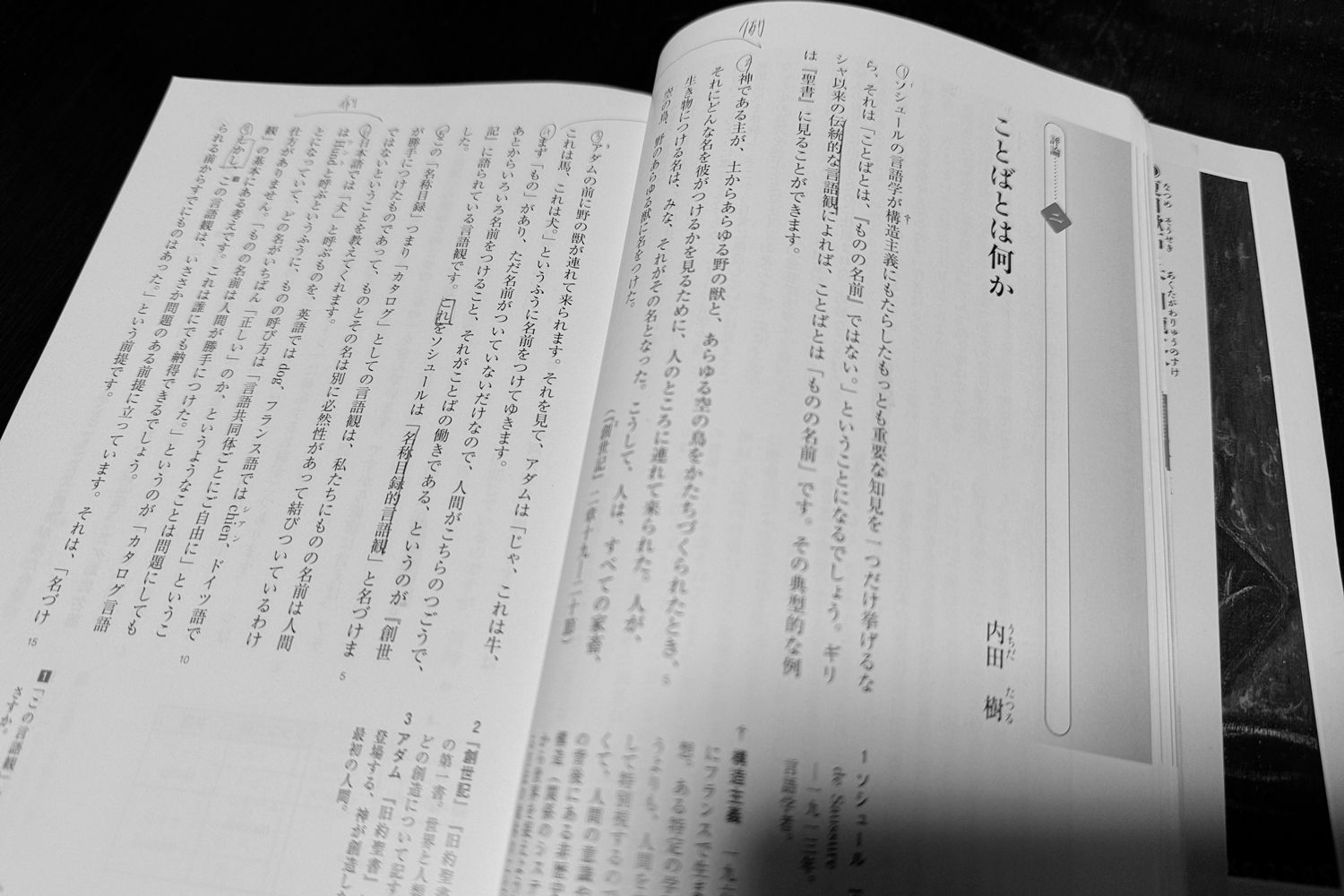


コメント