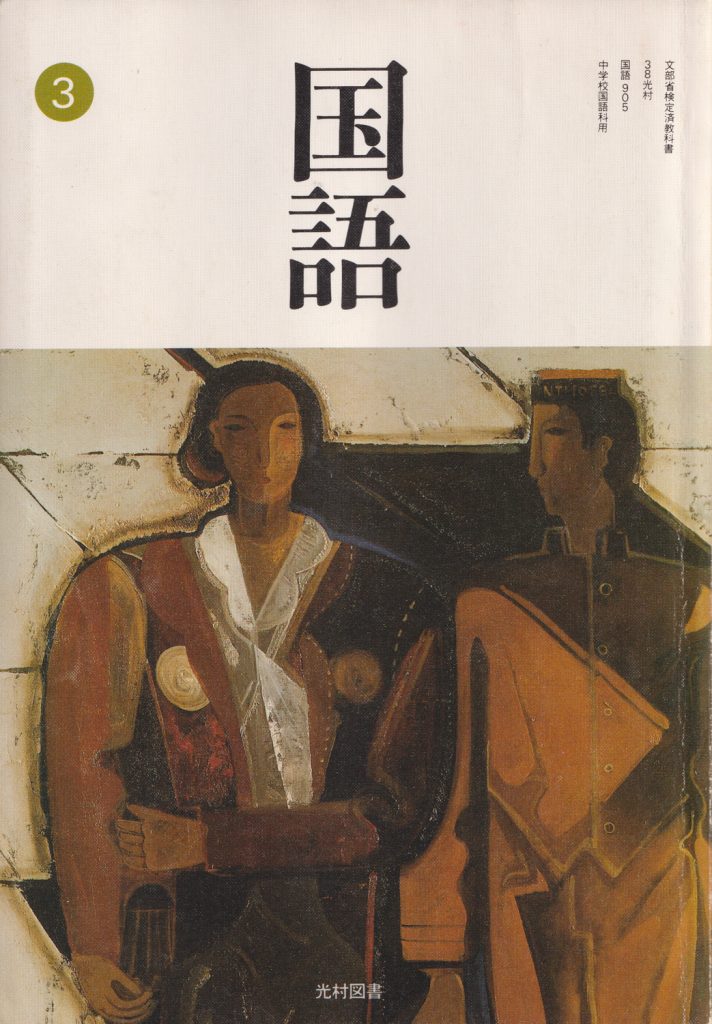
迂闊であった。「日本語の文法」に関するよりよい記述を、ある本から導いて、これに類似する記述を別の専門書から抽出しようではないか――という企てに、うつつを抜かしたのがそもそもの間違いだった。ある種のノスタルジックな思いはアナクロニズムのなれの果てだと気づいた時、網膜がちぎれるほどハレーションを起こしたのである。
いうなれば、事の発端は、こういうことになるのだが…。
昔読んだ「日本語の文法」に関する記述。その本は、中学3年用の国語教科書で、既に断捨離してしまっていて、手元に無かった。しかし、どうしてもあれをもう一度確認しておきたい――。
そこで私はどうしたか。
同じ本を、ヤフオクで探してみたのだった。
奇跡的にもその本が、ある古書店がリストアップしていたアイテムの中に見つかった。
私は早速それを買い求めた。――手元に今、それがある。もう二度と手放さないと心に誓った。
不可思議だ。そう、不可思議なのだ。ここまでのことを含めて、なんとも劇的な瑣末だと思った。私に発見されるまで、その古書店でひたすら待ち構えて眠っていたかのようである。
確かにこれで、「日本語の文法」に関する記述をあらためて読むことができた。これに類似する記述の専門書を見つける手立てはついた。だが、肝心なことは、もはやそんなことではなかった。私の体の内部に残影として消えなかった、他愛ないちっぽけな事件――。事件というのは大げさだ。ある出来事だ。誰も知らないある出来事…。そのことに背けず、敢えて何ものかに書き加えなければならぬと、教科書を読みながら思ったのだった。あれは確かにA子の教科書だった。
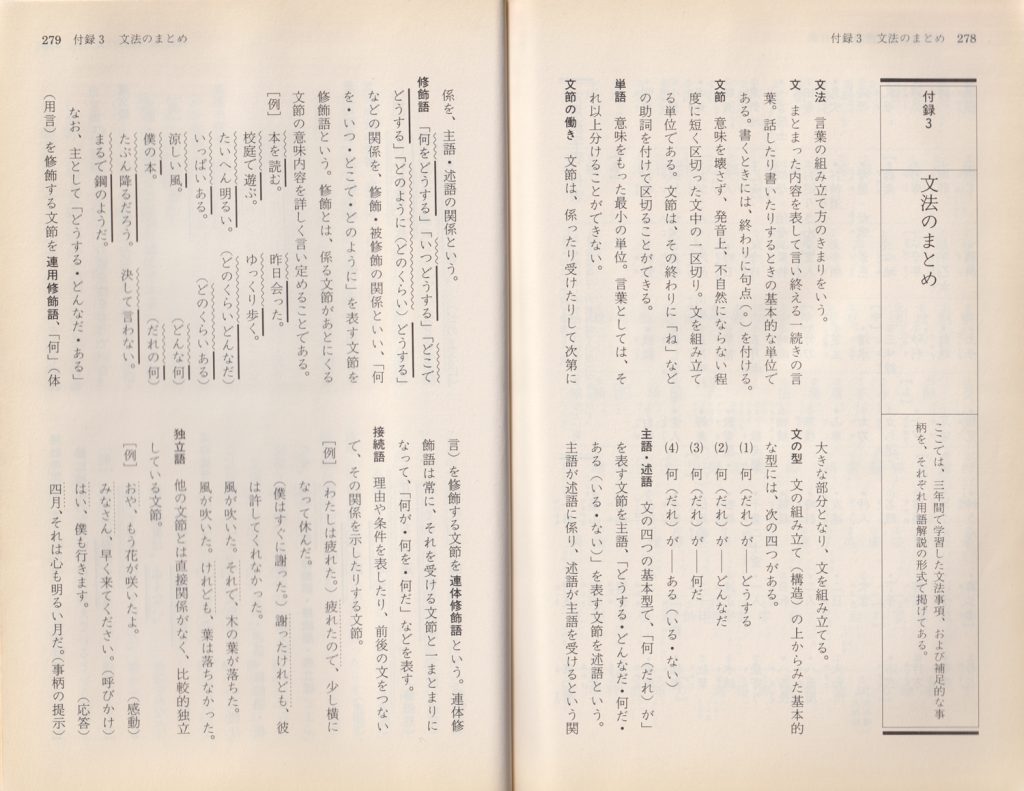
A子の国語教科書から
A子と出会い、そして彼女に恋した
断捨離してしまった元々の国語教科書は、A子が中学校で使っていた教科書だったのだ。
私とA子との関係については、「〈再録〉A子と教科書と魯迅」でふれている。20歳になったばかりの私と、13歳の中学生のA子。
地元の町で小劇団――劇団スパゲッティシアター――を結成し、そこで運命的にA子と出会った。やがて彼女が中学を卒業した暁に、私はA子から3年分の国語教科書を譲り受けたのだ。「〈再録〉A子と教科書と魯迅」では、そのあたりのことしか書いていない。だが、それでは不十分なのだ。
私はA子が好きだった。愛していた――。
だから彼女から、教科書を譲ってもらったのである。いうまでもないことだけれど、“運命的にA子と出会った”というのは、私の勝手な思い上がりに違いない。それに反して当時の私の心持ちは、もっと冷淡で、俯瞰的過ぎていた。
ある日私は駅ビルの2階の喫茶店にA子を呼び出して、差し向かいで談話したのである。話の途中で交際の申し込みをした。
20代の大人と、まだ高校生の男女なんて、どうかしている――。そんな思いは確かにあったが、矢も盾もたまらなかったのだ。しかしながら、A子は考えた末に、首を横に振った。奇妙なくらいに彼女は明るく笑顔だった。あれほど冷淡だったのに、何故か私の心はことさら熱を帯びて心臓が激しく動悸し、ともかく振られたのだと思った。あのA子に振られた――。家に帰ってから、私は真っ暗な部屋の中で、何もかもおしまいだということを悟った。
最後の電話
それからしばらくして、私は劇団を辞めたのだった。理由は複数あった。劇団自体が、演劇ではなくてコント集団に成り下がっていくのを感じてもいたし、A子と会うのもつらいという理由が大きく占めていた。
それまでの半月ほど、メンバーから“撤回宣言”を期待されて説得され続けていたのだけれど、結局は劇団を辞めることになったのだ。そうして突然、ある夜、A子から電話がかかってきた。
A子からの個人的な説得だった。辞めないでほしいというA子の気持ちは、私の心を苦しめるには至らなかった。だってA子は、私を振ったのだから。俺を裏切ったのだから――。俺だって、A子を裏切っても文句はないだろう――。
それくらいに絶望的な瑣末で、哀れで、みじめで、若気の至りだったのだ。恋に関しての柔軟な心持ち、いや、相手をおもんぱかる気はさらさら無かったのがあまりにも滑稽だ。しかし事実として、そういった外連味のない打開策・起死回生策は、25歳にも満たない私に到底ありもしなかったのである。青春は藻屑と消えた。

泡沫の影
それから17年後、メンバーと再会する機会があった。幾人かと親交の縒りを戻したのだ。
この時、私の密やかな願いは、A子との再会を果たすことであった。何もかもチャラにしたいという思い。あるいは明るい気持ちでもう一度、彼女との友人関係を築けるのではないかという淡い期待…。しかし、再会したメンバーは、ほとんどA子の消息を知らないどころか、あの頃のA子との思い出も、泡沫の影にすら感じていない素振りだった。私は落胆した。もちろん、A子と私との間で何があったかを知る者は一人もいないのだから、無理筋だということはわかってはいたものの、それにしても…。
私の密やかな願いは、その時、木っ端微塵に砕け散ったのだった。
かつて青年として無邪気すぎた私は、そのあおりを受け、再び自己の無邪気な心情に思いを馳せて9年前、「〈再録〉A子と教科書と魯迅」を書いた。それは正しいことだったと思う。
確かに9年前のその頃はまだ、劇団関係者と個人的なつながりがあったし、はっきりとA子との関係について、内情を書けなかったのである。人生の岐路にさしかかり、二つの道から片方の道を選択したということ。A子と訣別し、劇団とも別れる道を選んだということ――。
紆余曲折あって、昔のメンバーと再会を果たしても、A子との再会は果たせていない。さらに紆余曲折あって、3年前にメンバーとも交友を断絶し、私とかつてのメンバーとの関係は一切合切消えて無くなった。それでも尚、心残りなのは、A子との再会が未完のままだということだ。
A子はどこへ行った?
過去の後追いでもなく、虚無感もない。しかし。
彼女の居場所がいま、遠い所にあろうが、近い場にあろうが、私の心の些細な思惑が、そのうごめきが、決して彼女を離さず、已めないのである。これはいったいどういうことなのか、自分でもよくわからない。
私の知らない何かが、あの後あったのではないかという疑惑、疑念。私はそれを知らずして、今の自分で在るということへの、愚かな道化――。
いくらA子の教科書を棄ててしまっても、まだ何か燻っていたのだった。だから私は同じ本を抱えることにした。人はこうして哀れなものであるがゆえに、大人のふるまいを依然として秘密裏にしておくものなのである。きっと私だけではないはずだ。愚かなのは…。
会えるものなら、もう一度会ってみたい。A子に――。
追記:「教科書から高村光太郎『道程』」はこちら。
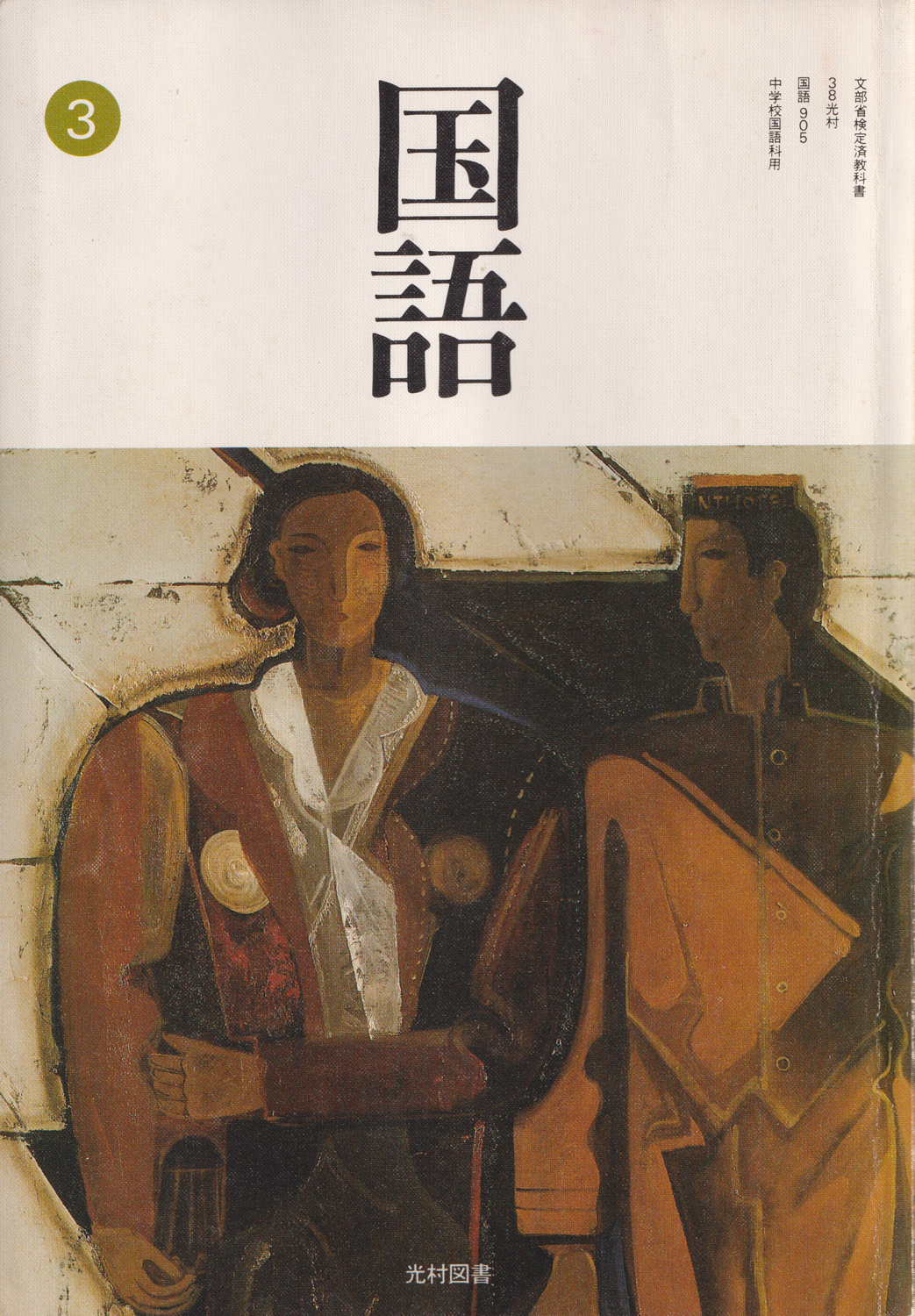


コメント