
その時代、街の大通りに軒を連ねていたのは、個人経営の商店だった。我が片田舎の町(街)の話である。
それが今では、どこも均一化して、無機質な雑居ビルばかりとなり、テナントは大概、学習塾である。四方を見渡せば、あちらこちらに名の知れた学習塾が、ひしめき合っている。
そうかといって、若い学生が群れる街の様相とはなっておらず、チグハグ感がある。
ありきたりな灰色のアスファルトに、街路樹の枯れ草が散乱して静寂なその風景は、大人どうしが闊歩して楽しめるだけの雰囲気も持ち合わせておらず、熟れた風も、熱情を帯びて甘ったるい香りも何も無いのだった。そんな街には、ホームレスの人々でさえ似つかわしくない。昔はその路地裏で、大人の夜のネオンがざわざわと猥雑な雰囲気をもたらしていたのである。
スキャンダルであるということ
最近のトピック。
ある若い男性タレントが、都内・新宿で「下半身を露出」し、公然わいせつの疑いで捕まった、というニュースを目にした。
例によってその者が所属する事務所では、タレント業務の活動を休止し、謝罪文を表明。
お互いに、慣れたものである。
やがて時期を見計らって、復帰を模索する。ビッグネームが保たれているかどうかが鍵。あくまでショービジネスの世界。もちろん個々の問題点はいくつもあるだろうが、お互いに、慣れたもの。ニュースのカテゴリーとしてはもはや、ありふれたトピックでしかないのだ。またか、という話である。
皮肉を込めて冗談をいうなれば、誰だって下半身くらい晒しているではないか――と、思う。ましてや私など、夏の暑い最中では短パン姿で、腿部から膝から足首に至るまで晒して、買い物がてら街を歩いていたりした。それを「下半身を露出」していたと表現したっていい。だがこれは、公然わいせつには――ならない。
つまるところ、ここからは冗談ではないのだが、「下半身露出」という表現では、何が問題になった事件だか、後々さっぱりわからないではないか…と。
スキャンダルとして掻き立てる…書き立てるということ
わからない人のために、敢えて具体を申し上げるならば、そのタレントは、少なくとも屋外で、自身の性器(男性器)を晒していたということらしい。今のところ、性暴力的な被害者はいないようだ。
ただし、詳細はほとんどわからないから、公道において下着を穿いておらず、下腹部剥き出しで小便をしていたところを通報されたのかもしれないし、公然と人前でフルチンになって騒いでいたのかもしれない。あくまで私の推測である。
それが通常時の萎んだペニスであったか、えらく硬直して勃起していたかどうかは不明であるし、実際のところ、そんなことまで詮索したくもない。愚弄である。そういう仔細な事実関係にまで注力するほど、私は暇ではないのだ――と見栄を張りたい。が、なんとなくこの事件、奇妙にきな臭さを感じてしまう。
いずれにせよ、この無機質で均一化されてしまった2025年の現代日本においては、その情報がほとんど文字として伝わってくるだけで、それ以上でもそれ以下の価値もない――ということの反復であり、そういう毎日が過ぎてゆくだけのことである。大方、何もかもがわからないまま、時が過ぎていく。そして皆、忘れていく。
つまり、一方では、地方の片田舎の街で、異様な数の学習塾が路上に「露出」し、もう一方では、都会のど真ん中で、「下半身を露出」する者がいた――という「不要なもの」どうしの、同一の無価値なトピックを、どう拾うかどうかの問題なのではないか、とも思うのだ。
スキャンダルとは、スキャンダルなものをスキャンダルとして書くことではなくて、そうではない事実までも含めてスキャンダルに思わせることを、スキャンダルというのである。
断っておくが、これは、捏造とは意味が違う。お笑い芸人さんのくだらない口喧嘩だって、スキャンダルに掻き立てられる時代であるがゆえに、ショービジネスでは食べてゆける、ということを思い知るべきである。
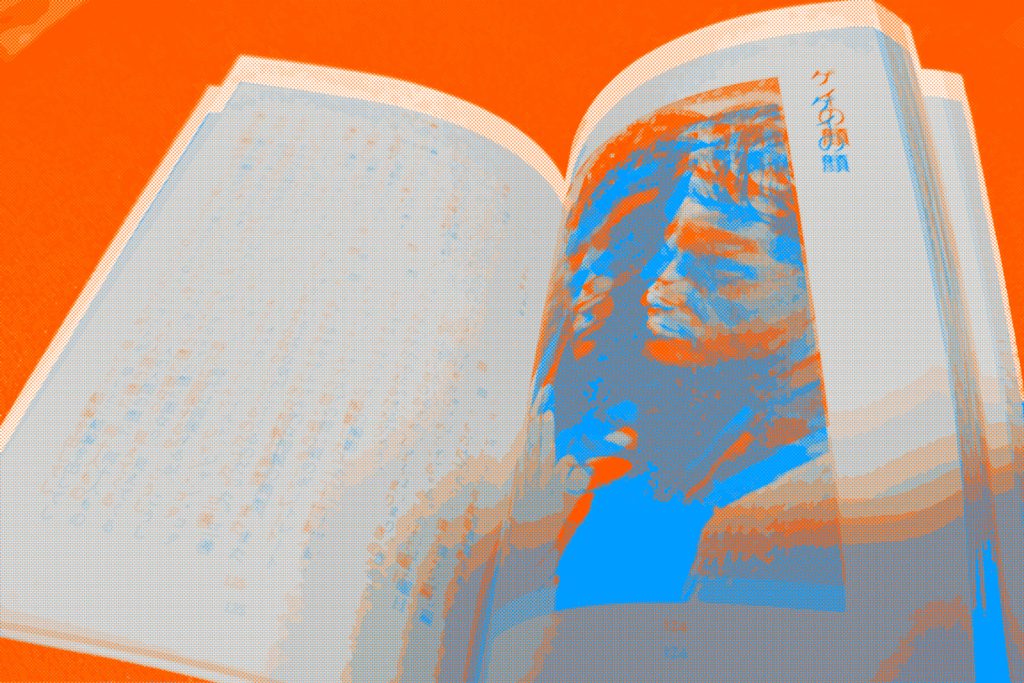
伴田さんの「ゲイの顔」
ここからが本題。
「不要なもの」の論議として、ここで私は作家・芸術家の伴田良輔氏のエッセイ「ゲイの顔」を取り上げたいと画策する。
伴田氏が素晴らしく皮肉を込めて、その文章体に「ゲイの顔」とタイトルを付けたのは、もうだいぶ昔のこと。そのエッセイが雑誌『sale 2』(No.33)に掲載されたのは、1988年である。
そして付け加えておくべきこととして、これを私が初めて読んだのは、エッセイが編輯された『愛の千里眼』(河出書房新社/1991年初版)であり、1991年から92年、あるいは93年の春のいずれか。まだ20歳そこそこの頃。
そう、この本でとくに懐かしいのは、非凡なるエッセイ「震える盆栽」である。
あの「震える盆栽」でまさに脳髄が震えたのとは対照的に、この「ゲイの顔」の文章が、単にゲイの人の顔に類型がほとばしり、すなわち類似点があるかのような感受的論説になっていることに、私は少なからず違和を感じ、放置した。むしろ、存在する彼のエッセイとしては、読者である私は放逐したつもりであったのだ。
おそらく伴田氏のこの手の仮説――ゲイの顔には類型がある――とやらは、全く根拠のない思いつきで、まともに読むのがバカバカしくなる、といったところで私の中では既に、オチはついていたはずであった。
なので、あれから数十年間、このバカバカしいと思ったエッセイをほとんど読み返すことをせず、今日までほったらかしにしてしまった末、平常時で、何かの拍子に突然、頭がおっ勃ったのは、そこにウォーホルのことが少しばかり記してあったからであり、急遽、再読を試みたのだった。
いまではこの「ゲイの顔」を、より知的に読み明かす、あるいは風雅を呼び起こすくらいのことはできるだろう、とは思うのである。
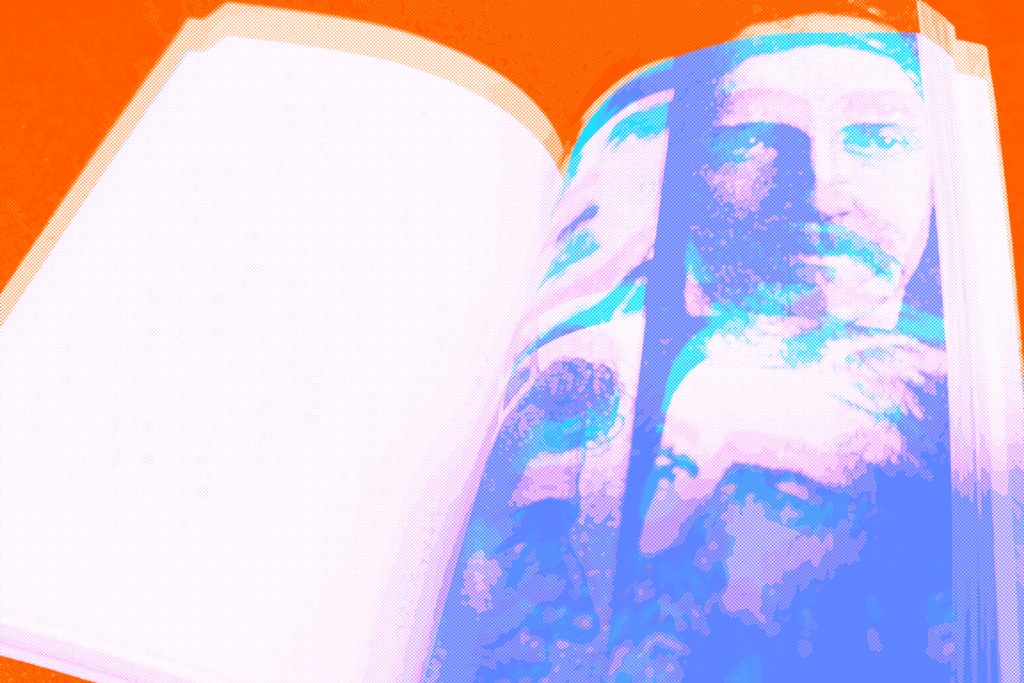
クエンティン・クリスプさんの顔
エッセイ「ゲイの顔」は、イギリスの写真家アンガス・マクベイン(Angus McBean)のポートレイト写真集を開き、ホモセクシュアル・ピープルの顔に刮目した――というところから文章が始まっている。ここではマクベインさんをマクビーンさんという日本語表記に改めさせていただく。
ホモの顔――。
少数者にとっては、それを聞いてムッとするに違いない。当時としては許されたかどうか知らないが、それにしても“ホモの顔”とは、露骨ないい回しである。
マクビーンさんが記録した、英国の人物クエンティン・クリスプ(Quentin Crisp)さんの若い頃のポートレイトを見ていると、彼の顔の中に、ホモの相貌の典型やら断片がつまっているのだという話。それが伴田氏の持論。
具体的には、三善英史、ジョー・オートン(Joe Orton)、オーブリー・ビアズリー(Aubrey Beardsley)、オスカー・ワイルド(Oscar Wilde)、ジャン・コクトー(Jean Cocteau)、セシル・ビートン(Cecil Beaton)、ボーイ・ジョージ(Boy George)を挙げている。
まあ、どう考えたって、伴田氏のいいがかりにすぎないのだ。
しかし、あの当時(90年代前半期)なら、それを読者が真に受けて承知してしまう危険は、じゅうぶんにはらんでいたと思う。大抵、ボーイ・ジョージさんの顔を引き合いに出せば、筋が通っているかのような錯覚を起こしかねないのだ。
ただ残念なことに、いや、単に私が不勉強なだけであるが、そもそも「ゲイの顔」を読んだ時、私は興味を全く示さなかったし、英国人のクリスプさんの顔すら思い浮かべられなかった。不寛容の極みである。
ホモセクシュアルからレズビアンの顔までそっくりに見えてくる?
このエッセイの中で出てくる、伴田氏がいう《ホモセクシュアル的な相貌の典型》(※原文ではホモセクシャル)とはいったい何だろうか。
ホモとかゲイと呼ばれる人々の、その典型なるものが、クリスプさんの顔と重なって、《何十人もの他人の顔がダブって見えてくる》というのだが、しかし…。
そう、しかしだ。伴田氏は持論ですら否定し、こう述べるのだ。
《そうではない。僕はクリスプの顔に、さらに、グレタ・ガルボ(レズビアンといわれた)やノエル・カワード、ジャン・マレーまで見てしまうのだ》
ええーーーー! と私はここで驚いて悶絶してしまうのである。
もともとの両親の仮託、いや違う、遺伝的な解釈を飛び越えて、類型的相貌に収まる顔。ゲイの顔。それが見抜けてしまうとは、伴田氏は恐るべき千里眼の持ち主ではないか。まさに、飄々と述べる。《千里眼とは、このことだ》。
そうか、この本のタイトル――『愛の千里眼』とは、このことを指していたのか。
壮麗なる鼻つき
いいがかりにしては、全く根拠がないともいえないのではないか…。
そう思えてきたので、私はネット検索でスマホを弄り倒し、どうにかこうにかマクビーンさんが撮ったというクリスプさんのポートレイト写真を探し出し、それをじっくりと眺めてみることにした。
そこで見たのは、伴田氏がいう、ほとんど目を閉じて両手を夢見る少女のようにしてアゴにあてたポーズの写真、とやら――。
ここでその写真をお見せすることができないのが心苦しいのだが、夢見る少女とは、いい得て妙ではないかと思った。
両手を合わせ、夢を見ている少女のような相貌。なぜそれが、少女でなければダメなのか。
この場合、少女が夢を見ている中味は、おそらく白馬の王子様を想ったり、あるいはシンデレラに成り代わって、うっとりとその貴公子的男性を見つめ、恋にうつつを抜かしている様相を指している。
クリスプさんがそのような相貌で、ほとんど目を下に向け、閉じる寸前かに見えるモノクロームの写真は、確かに照明からもたらされる光の陰影が、真っ白く化粧をしたクリスプさんの、やや白とび気味の顔に程よい感じを創り出し、男女の境界線を越えてくる美があると、私は思う。
したがって、伴田氏はこの写真を見たはずだ。このように述べている。
まず、何といっても鼻があやしい。ビアズリーには負けるが、あらゆる匂いとあらゆる穴をかぎあててしまうに違いないと思わせる、その鼻梁の張り具合、テカリ具合。鼻から上唇にかけての硬質のスロープの美しさはガルボを超えている。常に素晴らしい警句を吐いたという下唇の淫乱なふくらみが、鼻頂の肉づき、下アゴのふくらみと呼応しているのも素晴らしい。
伴田良輔『愛の千里眼』「ゲイの顔」より引用
先に列挙したジョー・オートンさんだとかの方々の顔を思い浮かべてみても、クリスプさんの顔立ちは、似ているとも似ていないとも思える。うーん、難しい。でも、先入観抜きでは、別段似ていないと思う。
問題は、顔が似ているか似ていないかではなく、それが《ホモセクシュアル的な相貌の典型》であるかどうかであって、どこにその典型が感じられるのか、私にはまださっぱり、経験不足でよくわからない。伴田氏のような、千里先までもお見通しさ、ヘヘン、というような千里眼の超能力が、私にはからっきし無い、ということの証左である。
伴田氏は注意深く、このようにも述べている。
マクベインの撮ったクリスプは、たぶん、三十歳ぐらいだろう。この頃のクリスプはホモセクシャルとして、すでに狭いロンドン社交界では自他ともに認める存在だったが、後々、カルト・ゲイ・ヒロインになるとは思ってもみなかっただろう。その張りつめた美意識で、フツーのホモセクシャルと自分を区別し、差別し、暴言をたびたび吐いたという。ゲイでありながら、他のゲイを憎んだのだ。プライドの高さこそ、しかし、ゲイの本領なのだ。
伴田良輔『愛の千里眼』「ゲイの顔」より引用

手と手を合わせて、ナムー
私が考える美意識とは、こうだ。
「誇り高き自尊心」と容赦なく駆り立てられる「醜悪に対する嫌悪」。それが常に自己に向けられ、さらに自尊心を越えようと研磨するこころざし。己を映す鏡こそ、弁証論的原理原則の要なのだけれど、そうした自己闘争(執念)の苦痛が、美意識の本質的正体なのではないだろうか。
そう、このテーマにはオスカー・ワイルドの小説、『ドリアン・グレイの肖像』(“The Picture of Dorian Gray”)がふさわしい。
この高い美意識の共通項が、ある人々の相貌を、見立てられるくらいに類型化するのであろうか。しかしおかしいことに、異性愛者にはそもそも異性愛者であることを示す類型の相貌があるとも、ないともいえないのであれば、やはりこの「伴田氏千里眼」は、ペテンの沙汰なのだろうか。
異性愛者の相貌は、おおむねその苦境の末のどこかで、美意識を持ち続けることを断念した挙句の果ての「崩れた類型」――ともいえなくもないが、これには反論が飛び交いそうである。
とどのつまり、同性愛者はいまだ、その苦境を自己に見いだし続けようとする生粋の探検家の姿なのではないか――というところで筆をおろしたい。
§
そしてここで私は、ポカをやらかしたことにハッとなって気づく。
肝心な、ウォーホルのことを書くのを忘れてしまったのだ。伴田氏はこの「ゲイの顔」で、ウォーホルにまつわる事柄をどう織り交ぜていたか…。
冒頭の学習塾の話なんて、どうでもよかったじゃない。もう遅い。やらかした。
手と手を合わせて、ナムー。
かの公然わいせつの疑いで捕まった男性タレントは、釈放されたものの、この世で身動きできる世界ががらりと変わってしまった――かと思われる。
でもその点でいうと、私自身は、彼がこの先の人生で、己がどう変わるのか、努力して変えていくのか、あるいは意固地になって変わらないでいるのか、そこに興味が全くないわけではない。
はっきり申し上げて、新宿二丁目のバーの付近で飲んで酔って、何かにときめいた挙げ句、何かのアクシデントでああなった、ということはいえるだろう。済まされないことは多々ある。
そこに、大衆がオスカー・ワイルドの世界を見いだしても構わないが、彼は彼であり、クリスプさんはクリスプさんである。鼻が高かろうが低かろうが、構うこっちゃないのだ。
自分の人生は自分で守り、自分で切り開く以外にないのである。
関連記事

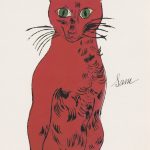

コメント